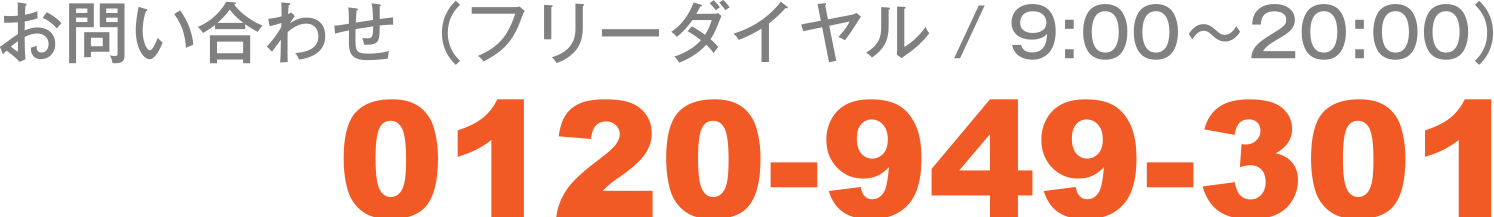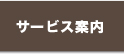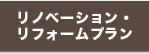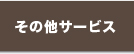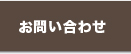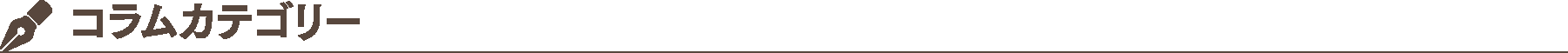НЛЄоЄЄЄЮСћВЛЅШЅщЅжЅыЄЫЄФЄЄЄЦ
ПЭЄЌЦќОяЪыЄщЄЗЄЦЄЄЄЏУцЄЧТПОЏЄЮРИГшВЛЄЌРИЄИЄыЄГЄШЄЯШђЄБЄщЄьЄЪЄЄЄтЄЮЄЧЄЙЁЃ
ЄНЄьЄЌЁжЄЊИпЄЄЭЭЁзЄШЄЄЄЈЄыЄшЄІЄЪОяМБХЊЄЪЅьЅйЅыЄЧЄЂЄьЄаЬфТъЄЯЄЪЄЄЄЮЄЧЄЙЄЌЁЂВЛЄЮТчЄЄЕЄфЛўДжТгЄЫЄшЄУЄЦЄЯЖсЮйЄЫТчЄЄЪЬТЯЧЄШЄЪЄъЁЂЄНЄЮЗыВЬЁЂСћВЛЅШЅщЅжЅыЄЌРИЄИЄЦЄЗЄоЄЄЄоЄЙЁЃ
ЦУЄЫЅоЅѓЅЗЅчЅѓЄЪЄЩЄЮЖІЦБНЛТ№ЄЧЄЯЁЂЮОЮйЄРЄБЄЧЄЪЄЏЁЂГЌЄЮОхВМДжЄЧСћВЛЅШЅщЅжЅыЄЌРИЄИЄфЄЙЄЏЄЪЄъЄоЄЙЁЃСћВЛЅШЅщЅжЅыЄЌЯУЄЗЙчЄЄЄЧВђЗшЄЧЄЄКЄЫЄГЄИЄьЄЦЄЗЄоЄІЄШЁЂКлШНЄЪЄЩЫЁХЊМъТГЄЧЗшУхЄЙЄыЄГЄШЄЫЄЪЄъЁЂЄНЄЮСћВЛЄЌЖсЮйЄЮРИГшЄђЫИГВЄЗЄЦЄЄЄыЄШШНУЧЄЕЄьЄьЄаЁЂСћВЛЄЮКЙЄЗЛпЄсЄфТЛГВЧхНўЄШЄЄЄУЄПЫЁХЊРеЧЄЄЌРИЄИЄыЄГЄШЄЫЄЪЄъЄоЄЙЁЃ
ЁжСћВЛЁзЄШЄЄЄУЄЦЄтЁЂЄНЄЮМяЮрЄЯЭЭЁЙЄЧЄЙЄЗЁЂЖёТЮХЊЄЪДФЖЄЫЄшЄУЄЦМѕЄБЛпЄсЪ§ЄтАлЄЪЄыЄтЄЮЄЪЄЮЄЧЁЂАьТЮЄЩЄьЄЏЄщЄЄЄЮЅьЅйЅыЄЫУЃЄЙЄыЄШЫЁХЊРеЧЄЄЌРИЄИЄыЄЮЄЋЁЂЕвДбХЊЄЪД№НрЁЪИТГІЮуЁЫЄђФъЄсЄыЄЮЄЯЦёЄЗЄЄЄЮЄЧЄЙЄЌЁЂАьШЬХЊЄЫЄЯЁЂЁжМѕЧІИТХйЁзЄђФЖЄЈЄПЄЋЄЩЄІЄЋЄЧШНУЧЄЕЄьЄыЄШИРЄяЄьЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
ЄНЄЗЄЦЁЂЄНЄЮЁжМѕЧІИТХйЁзЄђФЖЄЈЄЦЄЄЄыЄЋЄЩЄІЄЋЄђШНУЧЄЙЄыЄЫЄЂЄПЄУЄЦЄЯЁЂ
ЁЁЁСћВЛШяГВЄђМѕЄБЄЦЄЄЄыТІЄЮЛіО№ЁЪЄЩЄЮЄшЄІЄЪШяГВЄђМѕЄБЄЦЄЄЄыЄЋЁЫ
ЂЁЁСћВЛЄђНаЄЗЄЦЄЄЄыТІЄЮЛіО№ЁЪСћВЛЄЮФјХйЁІМяЮрЁЂСћВЛЄЮИЖАјЄШЄЪЄыГшЦАЄЮЩЌЭзРЁЂСћВЛЫЩЛпЁІДЫЯТЄЮЄПЄсЄЮТаНшЁІХиЮЯЁЫ
ЃЁЁУЯАшРЁЪДФЖЁЂУЯАшЄЫЄЊЄБЄыЙдРЏОхЄЮЕЌРЉЦтЭЦЁЫ
ЄЁЁСћВЛЄЮИЖАјЄШЄЪЄыГшЦАЄђКЙЄЗЛпЄсЄПОьЙчЄЮТЛМК
ЄШЄЄЄУЄПЛіО№ЄђСэЙчХЊЄЫШНУЧЄЙЄыЄГЄШЄЫЄЪЄъЄоЄЙЁЃ
ЄШЄГЄэЄЧЁЂСћВЛЅШЅщЅжЅыЄЯЖсЮйНЛЬБЦБЛЮЄЫИТЄщЄКЁЂУЯАшНЛЬБЄШДыЖШЄШЄЮДжЄЧРИЄИЄыЄГЄШЄтЄЂЄъЄоЄЙЁЃЮуЄЈЄаЁЂДыЖШЄЮЙЉОьЄфКюЖШНъЄЪЄЩЁЂЖШЬГГшЦАОхЁЂЩЌСГХЊЄЫЄЂЄыФјХйЄЮСћВЛЄЌРИЄИЄыЛмРпЄЌНЛТ№УЯЄЮЖсЪеЄЫРпУжЄЕЄьЄПОьЙчЁЂСћВЛЅШЅщЅжЅыЄЌЕЏЄГЄыЄГЄШЄЌОЏЄЪЄЏЄЂЄъЄоЄЛЄѓЁЃ

КЧЖсЄЮКлШНЮуЄШЄЗЄЦЁЂЪПРЎ24ЧЏ2Зю20ЦќЄЕЄЄЄПЄоУЯКлЗЇУЋЛйЩєШНЗшЄЌЄЂЄъЄоЄЙЁЃЄГЄЮЛіАЦЄЯЁЂЄЂЄыВёМвЄЮТхЩНМдЄЌЁЂЦќЗЯЅжЅщЅИЅыПЭЄЮЛвЄЩЄтЄПЄСЄЮЄПЄсЄЮЖЕАщЛмРпЄђГЋЙЛЄЗЁЂЄНЄЮАьДФЄШЄЗЄЦЅеЅУЅШЅЕЅыОьЁЪАьШЬЛдЬБЄЫЄтИјГЋЁЫЄђРпЮЉЄЗЄПЄШЄГЄэЁЂЖсЮйНЛЬБЄЮАьЩєЄЌЁЂСћВЛШяГВЄђЭ§ЭГЄЫЁЂАжМеЮСЄЮЛйЪЇЄЄЄШЁЂЫЩВЛСМУжЄЊЄшЄгЭјЭбРЉИТЄђЕсЄсЄПЄШЄЄЄІЄтЄЮЄЧЄЗЄПЁЃ
ЄГЄьЄЫТаЄЗЄЦЁЂКлШННъЄЯЁЂЁжЫмЗяСћВЛЄЮФјХйЁЂМяЮрЁІРМСЁЂИЖЙ№ЄщЁЪНЛЬБЁЫЄЮШяГВЄЮЦтЭЦЁІФјХйЁЂЫмЗяЄЮЗаАоЁЂЫмЗяСћВЛФуИКЄЮЄПЄсЄЫШяЙ№ЁЪВёМвТхЩНМдЁЫЄЌЙдЄУЄЦЄЄПСМУжХљЁЂХкУЯЭјЭбЄЮРшИхДиЗИЁЂИЖЙ№ЄщАЪГАЄЮЖсЮйНЛЬБЄЮШПБўЁЂЫмЗяЛмРпЄЮИјБзРЄЪЄЄЄЗМвВёХЊВСУЭХљЄЮДбХРЄЋЄщЁЂЫмЗяСћВЛЄЌМѕЧІИТХйЦтЄЮЄтЄЮЄЧЄЂЄыЄЋЄЩЄІЄЋЄђИЁЦЄЄЙЄыЁзЄШЄЗЄЦЁЂЄГЄьЄщЄЮНєЛіО№ЄђЖёТЮХЊЄЫИЁЦЄЄЗЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
ЖёТЮХЊЄЫИЁЦЄЄЕЄьЄПЦтЭЦЄЯМЁЄЮЄШЄЊЄъЄЧЄЙЁЃ
(1)СћВЛЄЮФјХй
РЏКіЬмЩИЄЧЄЂЄыДФЖД№НрЁЪ55ЅЧЅЗЅйЅыЁЫЄђМуДГФЖЄЈЄЦЄЄЄыЄтЄЮЄЮЁЂЩсФЬЄЮВёЯУЁЪЬѓ60ЅЧЅЗЅйЅыЁЫЄШЦБФјХйЄЮВЛЮЬЄЧЄЂЄъЁЂЦќОяРИГшЄЫНХТчЄЪБЦЖСЄђЕкЄмЄЙЄтЄЮЄЧЄЯЄЪЄЄЁЃ
(2)СћВЛЄЮМяЮрЁІРМС
ЦУЄЫВЛЮЬЄЌТчЄЄЄЄЮЄЯЅмЁМЅыЄЌЪЩХљЄЫХіЄПЄыВЛЁЂЅДЁМЅыЛўЄЮДПРМЁІЧяМъЁЂЛвЄЩЄтЦУЭЄЮЙтЄЄРМЄЏЄщЄЄЄЧЄЂЄъЁЂСћВЛЄШДЖЄИЄыЄЋШнЄЋЄЯМчДбХЊЭзСЧЄЌТчЄЄЄЁЃ
(3)ИЖЙ№ЄщНЛЬБЄЮШяГВЄЮЦтЭЦЁІФјХй
ИЖЙ№ЄщЄЮМчФЅЄЙЄыТЮФДЩдЮЩЄЮОЩОѕЄЯЫмЗяСћВЛЄЫЄшЄыЄтЄЮЄШЄЯИТЄщЄКЁЂЄоЄПЁЂЫмЗяЛмРпЄЮЛШЭбЩбХйЄЮИКОЏЄЫЄшЄъСћВЛЄЌФуИКЄЗЄЦЄЄЄыЁЃ
(4)ИЖЙ№ЄщАЪГАЄЮЖсЮйНЛЬБЄЮШПБў
ЖьО№ЄђНвЄйЄЦЄЊЄщЄКЁЂИЖЙ№ЄщЄЮН№ЬОГшЦАЄЫЄтЛВВУЄЗЄЦЄЄЄЪЄЄЁЃ
(5)ЫмЗяЄЮЗаАоЁІШяЙ№ЄЮЙдЄУЄЦЄЄПФуИКСМУж
ЫмЗяКлШНЄЮСАИхЄђФЬЄИЄЦЁЂШяЙ№ЄЌСъБўЄЮШёЭбЄђЛйНаЄЗЄЦЫЩВЛЙЉЛіЄђЙдЄЄЁЂЬфТъЄШЄЕЄьЄЦЄЄЄПТчВёЄЮГЋКХЄђУцЛпЄЙЄыЄЪЄЩСћВЛФуИКЄЮЄПЄсЄЫХиЮЯЄЗЄЦЄЄПЄГЄШЄђЩОВСЁЃ
(6)ХкУЯЭјЭбЄЮРшИхДиЗИЁЂЫмЗяЛмРпЄЮИјБзРЁІМвВёХЊВСУЭ
НЛЬБЄЫРшНЛРЄЌЧЇЄсЄщЄьЄыЄтЄЮЄЮЁЂЫмЗяЛмРпЄЯБФЭјЬмХЊЄЧЄЯЄЪЄЏЁЂАьФъФјХйЄЮМвВёХЊВСУЭЄЌЧЇЄсЄщЄьЄыЁЃ
АЪОхЄЮЄшЄІЄЪЖёТЮХЊЄЪИЁЦЄЄЮЗыВЬЁЂКлШННъЄЯЁЂЫмЗяСћВЛЄЌМѕЧІИТХйЦтЄЫЄШЄЩЄоЄыЄтЄЮЄШЄЗЄЦЁЂИЖЙ№ЄщНЛЬБЄЮРСЕсЄђЧЇЄсЄоЄЛЄѓЄЧЄЗЄПЁЃ
ЄГЄЮЄшЄІЄЫЁЂСћВЛШяГВЄЫЄшЄыЫЁХЊРеЧЄЄЯЖёТЮХЊЄЪЛіО№ЄЌИЁЦЄЄЕЄьЄыЄПЄсЁЂЛіАЦЄЫЄшЄУЄЦЗыЯРЄЯЭЭЁЙЄЧЄЙЁЃКлШНЄЧСшЄІЄГЄШЄЯЁЂЄЊИпЄЄЛўДжЄтМъДжЄтЄЋЄЋЄъЁЂЄЗЄЋЄтЗыЯРЄЌЭНТЌЄЗЄХЄщЄЄЄтЄЮЄЧЄЙЁЃЄЧЄЄыИТЄъЁЂЯУЄЗЙчЄЄЄЧВђЗшЄЧЄЄыЄшЄІЁЂЄЊИпЄЄСъМъЄЮЮЉОьЄђТКНХЄЗЁЂЄНЄьЄЧЄтЄЪЄЊЯУЄЌЄоЄШЄоЄщЄЪЄЄЄшЄІЄЧЄЗЄПЄщЁЂСсЄсЄЫЪлИюЛЮЄЫСъУЬЄЙЄыЄГЄШЄђЄЊДЋЄсЄЗЄоЄЙЁЃ

ЪлИюЛЮЁЁНТУЋИЕЙЈЁЪЄЗЄжЄфЁІЄтЄШЄвЄэЁЫ
ЄЗЄжЄфСэЙчЫЁЮЇЛіЬГНъЁЁНъФЙ ТчКхЪлИюЛЮВёНъТАЁЪ2000ЧЏХаЯПЁЫ
ДыЖШЄфИФПЭЄЮЫЁХЊЅШЅщЅжЅыЄЮИђОФЁІЭНЫЩКіЄђУцПДЄЫЁЂДыЖШЁІЫЁПЭЄЮЬђАїЁЂТчГиЙжЛеЄЪЄЩЄтЬГЄсЄЦЄЄЄоЄЙЁЃ
Ёк ЫмЪИЕЛіДЦНЄЁЇ НЛЁІЖѕЁІДжЁЁЪдНИЩє Ёл